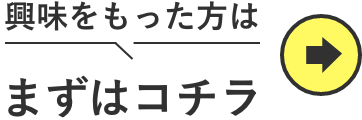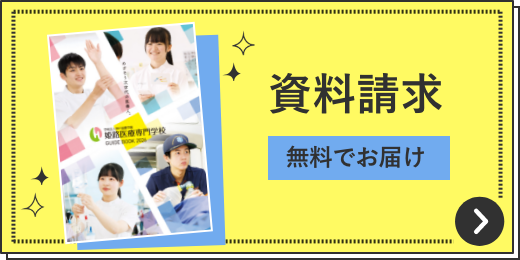臨床工学技士が扱う医療機器 ~人工呼吸器編②~
前回のブログはこちら
酸素と二酸化炭素のガス交換を行う肺胞ですが、病気等で肺胞に空気が送り込めず、ガス交換ができなくなることがあります。
そんな時、呼吸を補助するのが「人工呼吸器」です。

例えば、病気で空気が吸いづらい患者様に対しては、空気に圧力をかけて(陽圧)、肺に無理やり空気を送り込みます。
50年以上前は、体をドラム缶のような管に入れて大気圧より低い陰圧をかけて呼吸させる人工呼吸器もありました。(鉄の肺とも呼ばれていました)
しかし、現在ではガスを送り込む陽圧換気が主流です。
他にも、肺の炎症などで呼吸不全になってしまった患者様には、空気を吸い込む力や吐き出す力を補助します。
しかし、肺が弱りきってしまい、いくら空気を送り込んでもガス交換が行えない状態になってしまうと、人工呼吸器では対応できなくなります。
そのような時、出番となるのが「エクモ」です。
新型コロナウイルス感染症が流行したときに、名前を聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
「エクモ」とは、人工心肺装置(Extracorporeal Membranous Oxygenation)の略で、肺そのものの機能を代行して、血液に直接酸素を送り込む医療機器です。

臨床工学技士は、「人工呼吸器」や「エクモ」の使用前後のメンテナンスはもちろん、使用中の状態、また患者様の容態にも気を配っています。
▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽
他にも、本校には様々な医療機器があります。
オープンキャンパスでも紹介しているので、ぜひお越しください。
お待ちしています!