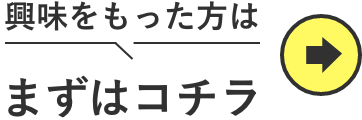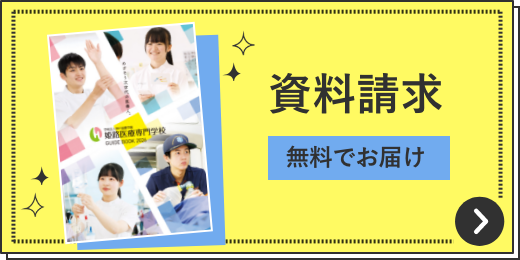医療を支える電気のシゴト

こんにちは!
いつも学校ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今日から、ブログを3本立て‼
臨床工学技士科から、私たちの生活(身の回りにあるモノ)と医療をテーマにお話ししたいと思います‼
1本目のこのブログでは、私たちの生活に欠かせない「電気」と医療の話。
2本目のブログテーマ:空気と呼吸のフシギ
3本目のブログテーマ:音と医療のつながり
電気は必要不可欠!そんな電気の役割って?
朝、スマホのアラームで目を覚まして、電気をつけて部屋を明るくする。
夜はゲーム機やパソコンで遊んだり、動画を見たり。
気づけば一日の始まりから終わりまで、私たちは電気に囲まれて暮らしています。

でも「電気って便利だな」だけじゃなくて、
実はもっと大切な役割を持っているんです。
病院では、電気が人の健康を守るために欠かせない存在なんです。
病院での電気の位置づけ
病院で使われる機械のほとんどは電気で動いています。
人工呼吸器や人工透析装置、人工心肺装置、そしてペースメーカー。
これらはすべて、患者さんの身体を支えるために欠かせない機器です。

つまり、医療現場は「電気が人を支える場所」でもあるんです。 そういわれると、確かに…と納得いただけるのではないでしょうか。
電気の知識=人を救う!?
私たち臨床工学技士は医療と工学のスペシャリストといわれます。
電気の知識があるからこそ、機器のトラブルを防ぎ、
患者さんの身体を守ることができるのです。

今、高校で物理の授業を選択している方もいると思います。(物理は苦手…という方もいるのでは(笑))
高校の物理で学ぶ電気回路や電圧の話が
実は医療現場でとても重要な役割を果たしていることを知ると、
勉強の意味が少し変わって見えるかもしれませんね。