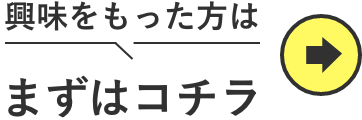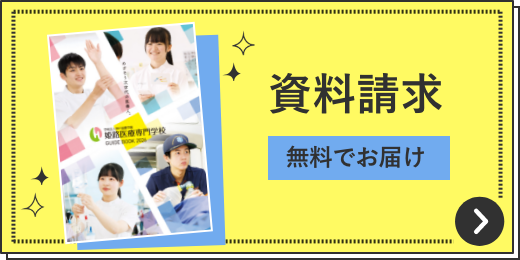空気と呼吸のフシギ

みなさん、こんにちは!
臨床工学技士科のブログへようこそ。
今回は”私たちの生活と医療ブログ”3本シリーズの2本目、空気と呼吸のフシギについてご紹介します。
空気って何?呼吸ってどんな仕組み?
「空気って、ただの透明なものじゃないの?」
「呼吸って、勝手にしてるだけでしょ?」
そんなふうに思っていたら、ちょっともったいないかも。実は、空気と呼吸には、びっくりするくらいたくさんの“しくみ”と“ひみつ”がつまっているんです。
私たちの体、呼吸と空気
私たちが吸っている空気の約8割は「窒素」、約2割が「酸素」。

この酸素が、体の中でエネルギーを作るために使われています。
つまり、酸素がないと、体は動けなくなってしまうんです。
でも、空気はただ吸えばいいわけじゃありません。
肺の中で酸素を取り込み、二酸化炭素を吐き出す――この「ガス交換」がうまくいかないと、体に不調が出てしまいます。
病気やけがで呼吸がうまくできないとき
私たちは無意識に呼吸をしていますが、病気やけがでうまく呼吸ができないときに活躍する医療機器が人工呼吸器。空気の量や圧力を調整して、肺に酸素を送り込むしくみです。
この人工呼吸器を操作・管理するのが、臨床工学技士という専門職。
患者さんの呼吸状態を見ながら、機器の設定を細かく調整して患者さんの呼吸をサポートしています。

空気の流れや圧力、酸素濃度など、理科で学ぶ内容がそのまま医療機器の仕組みに関係しているんですよ。
例えば、風船に息を吹き込むと、空気が中に入り、ゴムが外に向かって広がります。
これは「空気の圧力」が風船の内側から押しているから。
空気には目に見えないけれど、ちゃんと“力”があるんです。
風船を膨らませるときの空気の力は、人工呼吸器が肺に空気を送る仕組みと似ています。
風船を膨らませる――身近な動作の中にも、医療につながるヒントがたくさんあります。そんな気づきが、医療の世界への第一歩になるかもしれませんね。